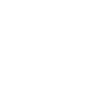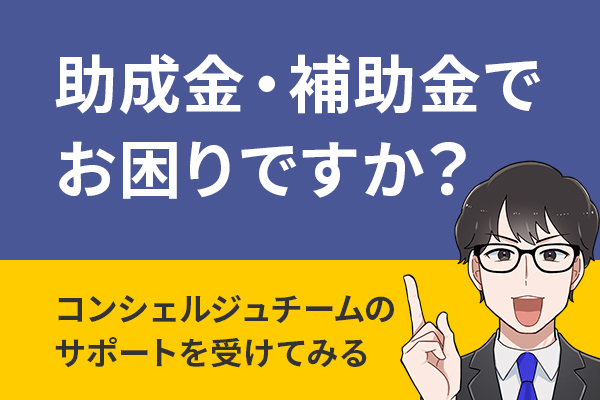助成金申請の落とし穴?提出先を間違えないための申請初心者向けガイド
2025年12月9日

目次[開く]
助成金申請のはじめの一歩!提出先を理解する重要性
助成金申請を成功させるためには、まず提出先を正確に理解することが重要です。
なぜなら提出先が異なると、必要書類や手続きが異なる事が少なくないからです。
このため、提出先の窓口を事前に把握することが、申請のスムーズな進行に直結します。
助成金の提出先を理解するために、まずはどのような団体が助成金を提供しているかを、次からご紹介します。
助成金はどんな団体が窓口になっているの?
助成金は、厚生労働省や各自治体、さらには独立行政法人や公益財団法人などの団体から出ており、同時に窓口の機能も担います。
助成金申請の提出先は、主に次のような団体です。
- 厚生労働省
- 地方自治体
- 民間団体
- 公的な団体など
さまざまな団体がある理由としては、それぞれ役割や助成金を提供する意味が異なるからです。
たとえば厚生労働省では、雇用や職場環境の改善に関する助成金を多く取り扱っています。
「キャリアアップ助成金」や「両立支援助成金」などがその一例です。
一方、自治体の助成金は、中小企業向けの場合は産業振興や商業活動を支援する担当課が窓口になることが多く、地方性が織り込まれていることはもちろん、それぞれの担当課の特性に特化した内容になっています。
さらに、独立行政法人や公益財団法人、支援機構などからも、事業分野に応じた専門的な助成金が提供されています。
下記でもう少し詳しく紹介していきます。
助成金提出先1:厚生労働省関係
厚生労働省では、主に雇用関連や労働環境の改善に関する内容を中心に、多くの助成金の申請を受け付けております。
例えば次のような助成金があります
| 助成金名 | 概要 |
| キャリアアップ助成金 | パートやアルバイトを正社員にすることで助成金が受けられる制度 |
| トライアル雇用助成金 | 就職が困難な求職者を短期間で試験的に雇用することで助成金が受けられる制度 |
| 両立支援等助成金 | 育児や介護と仕事を両立させるための支援をする制度 |
厚生労働省の名義で助成金が提供されていますが、申請書の提出先や問い合わせ窓口は、主に労働局などが担当します。
労働局とは、厚生労働省の地方支分部局の一つで、各都道府県に設置されています。
また、労働局の管轄下には「労働基準監督署」や「公共職業安定所(通称:ハローワーク)」などがあり、これらが窓口や問い合わせ先となります。
助成金提出先2:地方自治体
各自治体からも、様々な助成金が提供されています。
地域振興や創業支援を目的とした中小企業向けの助成金が多く、商店街の活性化を図る制度や、空き店舗の利活用を支援する取り組みなど、自治体ごとに独自の支援制度が特徴です。
一方で、助成金の名称が「○○支援事業」や「○○補助金」といった形で表記されている場合もあり、「助成金」というキーワードだけでは検索にヒットしないことがあります。そのため、自治体のウェブサイトで最新情報を確認し、詳細を調べることが重要です。
さらに、市民向けの助成や手当も多岐にわたるため、適切な制度を見つけられない場合は、事業者向けのページから産業分野を絞り込むなど、探し方にも工夫が求められます。
助成金提出先3:公的な団体
独立行政法人などの公的な団体からも、特徴的な助成金が出ています。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は、高齢者や障害者、求職者の雇用支援に特化した助成金を提供しています。
また、独立行政法人スポーツ振興センターからはスポーツに関連した助成金、独立行政法人環境再生保全機構からは、環境問題や地域の社会課題を解決する活動に対して助成金が出ています。
助成金提出先4:公益財団法人
公益事業を行う法人である公益財団法人からも助成金が出ています。
助成内容の例は次の通りです。
| 団体名 | 名称 | 概要 |
| 公益財団法人ヤマト福祉財団 | 障がい者給料増額支援助成金 | 障がい者の給料増額に努力し取り組む事業所・施設に対し、さらに多くの給料を支払うための事業の資金として助成 |
| 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター | 北のふるさと事業承継支援ファンド | 道内小規模企業者の円滑な親族外事業承継を支援 |
| 公益財団法人北洋銀行中小企業新技術研究助成基金 | 北洋銀行ドリーム基金 | 中小企業等が行う新技術及び新製品の研究開発に対する助成 |
| 公益財団法人東京都中小企業振興公社 | 新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(経営改善計画策定による経営基盤強化支援)(一般コース) | 「これまで営んできた事業の深化又は発展」に取り組み、これが経営基盤の強化につながると認められた場合に、当該取組に必要な経費の一部を助成 |
上記で紹介した内容はごく一部で、助成金と補助金を合わせると1万種類以上もあると言われています。
具体的な助成金別の申請先・提出先例
助成金の申請先は主に公募を行っている団体です。
しかし、まれに書類の提出先が複数ある場合もあります。
例として、次の3つの助成金の申請資料提出先について紹介します。

以上のように、助成金によって書類の提出先などに違いがあります。
制度の理解も大切ですが、同様に提出先やスケジュールについても理解することが重要です。
提出先が分からない!助成金の提出先を調べる方法
助成金の提出先が分からない場合は、以下の方法で調べることができます。
1.公式サイトを確認する
各助成金には公式サイトや専用ページが設けられている場合が多く、詳細が掲載されています。また、ガイドブックやリーフレットが用意されていることもあり、サイト上で確認することが出来ます。提出先や問い合わせ窓口が明記されていることがほとんどです。
2.ガイドブックや資料を確認する
助成金ごとにガイドブックやリーフレットが用意されている場合は、提出書類や手続きの詳細、提出先などが記載されています。これらを事前に入手して確認することをおすすめします。
提出先に迷った場合は、まず公式情報を確認し、不明点があれば遠慮せずに問い合わせることでスムーズに手続きを進められます。
助成金の3つの提出方法
助成金を申請する際には、窓口提出、郵送、電子申請のいずれかの方法を選ぶことになります。
しかし、助成金によっては提出方法が限定されている事もありますので、申請を検討している助成金制度の概要をご確認ください。
3つの提出方法のメリットとデメリットについて紹介します。また併せて、3つ以外にもできる助成金の申請方法も解説します。

窓口に直接提出
助成金を申請する際、窓口に直接提出する方法が一般的です。
確認したいことがあればその場で担当者に聞くこともでき、名刺をもらっておけば何かあった場合に相談しやすくなります。
しかし、次のようなデメリットもあります。
- 受付してもいつ呼ばれるかわからず、どのくらいの時間がかかるかも予測できないため、そのあとのスケジュールを組みづらい
- 時間帯によっては専用駐車場に車を停められないこともある
- 窓口に行くまでに時間がかかる
特に、初めて助成金を申請する場合には、窓口に行って書類を提出するのがオススメです。
郵送での提出
助成金によっては、郵送での提出が認められています。
郵送する際は普通郵便ではなく、郵便事故防止のために、特殊郵便(特定記録または簡易書留)による送付が求められるため注意が必要です。
また、申請期限内に書類が到着しないと不受理となるため、余裕を持って早めに郵送しましょう。
そして郵送を利用する際も、書類の不備がないか事前に十分確認することが重要です。
電子申請
厚生労働省で用意している助成金については、電子申請も可能です。
電子申請のメリットは次の通りです。
- 窓口が閉まっている時間でも、時間を気にせずに申請や申請状況の確認ができる
- 一度入力した情報は繰り返し自動反映されるので、入力が便利になる
電子申請には、g-Biz(複数の行政サービスを利用できる共通認証システム)のIDが必要になります。事前に取得しておくといいでしょう。
ここまで、助成金の申請方法について、窓口、郵送、電子申請の3つを紹介してきました。
これ以外にも、社労士に申請を依頼する方法もあります。
費用をかけて社労士に申請を依頼する方法
助成金の申請は事業者が自分で行うことも可能ですが、費用をかけて、社労士に申請サポートを依頼する選択肢もあります。
依頼する内容によって料金も変動しますが、申請にかかる時間や手間を大幅に削減できる、書類のミスや不備のリスクを減らせるなどのメリットがあります。
しかし、「報酬や手数料の支払いでコストが増える」「社労士の選び方が分からない」などのデメリットもあります。
そのため自分で行うか、社労士に依頼するかはしっかりと検討して選ぶ必要があります。
なお、厚生労働省が管轄する助成金における申請書類の作成や書類提出の代行は社労士の独占業務であり、社労士以外に申請代行を依頼することは認められていません。
価格を抑えて時間も削減できる「社長の顧問」
最小限のコストと最低限の手間で、助成金申請に関する課題を解決できるのが「社長の顧問」です。
専門知識を持つ専属スタッフが貴社を担当し、申請の準備などをしっかりとサポートいたします。
サービスの流れとしては次の通りです
- 会員企業様の課題やビジョンを丁寧にヒアリングする
- 専属スタッフが、活用できそうな助成金・補助金を探してご提案する
- 必要な書類や申請手順の説明など、助成金申請までのサポートを行う
- 必要なら社労士のマッチングサービスを提案する
- 1本目の助成金申請が終わっても、約1万種類の制度から活用できそうなものを更に探して提案する
専門家が必要となった場合には、単発で依頼できる専門家とのマッチングも可能です。
(※専門家への相談は別途費用がかかります)
特に助成金の申請を一度も行ったことがない方で、不安を感じている場合は、ぜひ「社長の顧問」をご活用ください。
申請を自分で行おうと検討されている方でも、経験がないと試行錯誤を繰り返しながら進める必要があり、予想以上に時間や手間がかかることがあります。結果として、「専門家に委託したほうがコストを抑えられた」と感じるケースも少なくありません。
さらに、途中で申請を断念してしまうと、それまでに費やした時間や労力が無駄になる可能性もあります。
費用対効果を考えると、弊社サービスを利用することで、効率的かつスムーズに申請手続きが進められる場合が多いため、ぜひご検討ください。
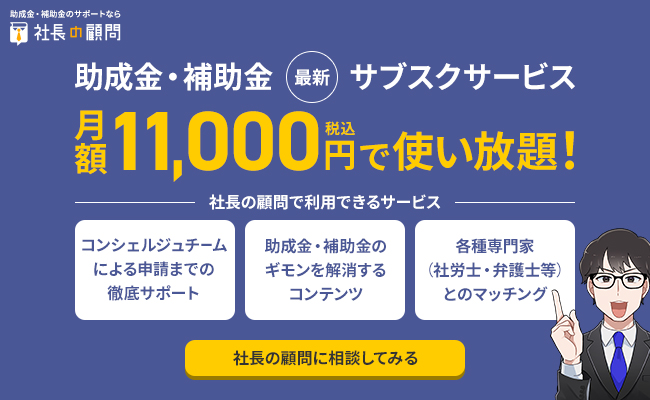
まとめ:助成金の手続きを理解して効率的に進めよう
助成金の申請を成功させるためには、正確な提出先と手続きを理解することが不可欠です。
都道府県労働局やハローワーク、各種支援機関の窓口を把握することで、申請ミスを防ぎ、スムーズな手続きが可能になります。
また、直接提出や郵送、専門家への依頼といった提出方法も適切に選択することで、申請がより確実に進みます。
正確な情報と準備をもとに、自社に適した助成金を最大限に活用しましょう。
「助成金・補助金の知識」
の記事

助成金は何でこんなにめんどくさいんだ!その正体と解決方法をご紹介
「助成金を申請するために色々調べたけれど、結局分からなくなって諦めた」 「助成金申請はめんどくさいと聞いて、二の足を踏んでいる」 「いろいろとやってみたけど、助成金申請が進まず途方に暮れている」 そんな人も多いのではないでしょうか。 数ある助成金の中から1つを選ぶのは大変で、申請作業はもっと大変です。 そこでこの記事では、「めんどくさい」と感じてしまう要因を見極めて、一歩前に踏み出すための解決方法をご紹介します。 助成金はめんどくさいのではないか?と一歩踏み出せていない人や、踏み出した道が険しくなって抜け出せない人は、この記事をきっかけに進んでいただければ幸いです。
2025年12月9日

【店舗運営に活かせる助成金】膨らむ理想を支援制度で現実に!
店舗運営を始める際に、「改装費が足りない」 「設備投資の資金を確保したい」 「かっこいいウェブサイトを安価で作成したい」 など、資金面の課題に直面することは少なくありません。 こうした費用を抑えつつ、理想の店舗づくりを実現するために、助成金や補助金の活用を検討してみてはいかがでしょうか? ただし、助成金や補助金にはさまざまな種類があり、自社に適したものを見極めるだけでも大変です。また、申請手続きが複雑で、後払いが基本といったハードルもあります。 準備不足のまま進めると、受給できないケースも多いため、事前の情報収集が欠かせません。 本記事では、店舗運営に役立つ助成金・補助金の種類、申請時の注意点を詳しく解説します。資金の負担を抑えながら、理想の店舗を実現するために、ぜひ参考にしてください。
2025年8月5日

2025年育児・介護休業法改正:6つのキーワードで分かりやすく解説
2025年4月から段階的に施行される育児・介護休業法の改正は、柔軟な働き方を促進し、離職防止を図るため、事業主に新たな対応が求められます。 本記事では、改正内容を11のポイントに整理し、企業が準備すべき具体策を6つのキーワードでわかりやすく解説します。 施行日までにしっかりと対応を進め、働きやすい環境づくりを目指しましょう。 また、法改正への対応にあわせて活用できる助成金についても紹介していますので、ぜひご覧ください。
2025年8月5日

助成金をもらえない原因はこの7つ!失敗を防ぐための注意点と成功のコツ
助成金は返済不要で使い道の自由な制度であり、中小企業の強い味方ですが、その分満たさなければならない条件が多く複雑です。 たった1つ条件を満たさないだけで「もらえなかった」というケースもあります。事業で忙しい中、なんとか申請したのに助成金をもらえないというのは、やりきれませんよね。 そこで本記事では、助成金をもらえない原因とその解決策について解説します。申請が通らないリスクを回避するためにぜひご覧ください。
2025年8月5日