-
トップ
- 社宅の顧問
 で
で
従業員の賃貸住宅を
おトクに借りませんか?
従業員が賃貸借契約されているお部屋を
企業で借上げ契約することで、
従業員と企業にとってメリットがあります。
社宅の顧問とは
企業に勤めている従業員が 、賃貸物件を社宅化して住むことができる住宅の福利厚生サービスです。
これまでの社宅は、煩雑な業務や管理費がかかるといった理由で一部の企業のみに導入されていましたが、
社宅の顧問では管理費も抑えながら業務を効率化することで、賃貸借契約をしている全従業員を対象に、ご利用いただきやすくなりました。
導入のメリット
- 従業員
- 可処分所得アップで
モチベーションUP - 総務人事
- 採用強化
離職率低減 - 経営陣
- 社会保険料の
会社負担軽減
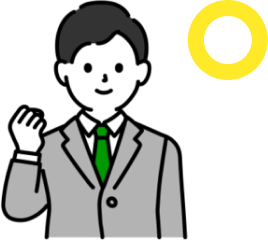
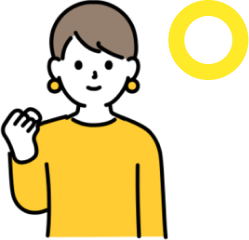
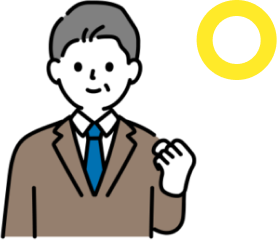
なぜ
そんな効果が期待できるの?
令和4年4月1日現在の法令
従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、 従業員から1ヶ月当たり一定額の家賃 (以下「賃貸料相当額」といいます。) 以上を受け取っていれば給与として課税されません。
国税庁HP No.2597より
というルールを
利用することで、
従業員にも企業にも
メリットが生まれます。
かんたん
導入シミュレーション
従業員数
人
平均年収
万円
- ※平均年収76万円~1,858万円の範囲で入力ください。
- ※全国健康保険協会の東京都の令和4年度の保険料額表から社会保険料を算出しています(介護保険第2号被保険者非該当)。
- ※家賃は給与の25%として算出しています。
従業員の
社会保険料の負担減
※源泉所得税の減少額は含まず
導入後の
手残り増加金額/年
約円
UP
企業が負担する社会保険料
※1人あたりの社会保険料/年
社宅の顧問導入前
約円
社宅の顧問導入後
約円
導入後の
年間の社会保険料負担額/年
※人が社宅の顧問を利用(従業員の25%利用とする)
約円
削減
導入例
A
基本給30万円/家賃10万円の
従業員の場合
従業員の場合
基本給から家賃の半額分を減額
/残りの半分を給与控除
所得税の負担が軽減(手残りUP)
従業員、企業ともに
金銭的メリットあり
B
基本給30万円/住宅手当5万
/家賃10万円の従業員の場合
/家賃10万円の従業員の場合
基本給から家賃の半額分を減額
/残りの半分を給与控除
所得税の負担が軽減(手残りUP)
従業員、企業ともに
金銭的メリットあり
導入フロー
-
01導入準備
・社宅規程の作成
・給与規程に条文追加対応
・入居禁止事項誓約書の作成
・入居同意書の作成まずはご相談下さい。
社宅の顧問について、専門的な社労士への相談が可能です。複雑な規程変更なども、過去導入企業の実績をもとにサポートさせて頂きます。 -
02導入時
・従業員向け説明会の実施
・労使協定の締結(労働組合 or 従業員代表)
・名義変更の手続き(今の住居を社宅にする場合)
・所轄の労基署へ資料提出お手伝いが可能です。
新入社員様向けに制度を導入した際の説明会のサポートや現在従業員様が借りている物件を当社にて名義変更することが可能です。
でも、
導入してからが
大変なのでは?

※規程の変更については他社事例の提示。社労士様への相談も別途有料で可能となります。
社宅の顧問なら
面倒な社宅管理業務を
500円/戸で解決します!

よくある質問
-
Q企業が導入しない理由で多いものは何ですか?Aそもそも制度を知らない、社宅管理業務が増える、規程の変更がめんどくさい、全社員が対象ではないなどの理由です。
-
Q従業員が今住んでいる物件を社宅にすることはできますか?A可能です。ただし物件によっては、名義変更手数料を管理会社から請求されるケースがございます。会社様で負担される場合、従業員様で負担される場合と二通りありますので他社様の実績等を踏まえて、ご提案させていただきます。
-
Q基本給を減額するのは問題ないのでしょうか?A問題はございません。ただし不利益変更に当たるので、就業規則・ 給与規程を改定する場合には労働契約法第8条から10条に従ったうえで就業規則・給与規程の改定手続を取るか、対象従業員の合意を得たうえで労働契約書のまき直しや労働条件通知書を再作成し、労働条件変更に関して書面にて同意を取る必要があります。
-
Q家賃の半分を給与から減額した際、最低賃金を割ってしまったらどうなるのでしょうか?A最低賃金額を下回ることはできないので、最低賃金額以上になるように減額分を調整し、減額できなかった不足家賃相当額については給与から控除する必要があります。なお、給与控除に当たっては賃金控除の協定書の締結が労働組合等と必要なので、社宅料控除について協定書の控除項目に入っているか確認が必要です。
-
Q残業代の扱いはどうなりますか?A減額前の基本給等を基礎として割増賃金の計算すれば、現状と変わりません。労働者にとって有利な内容となりますので、労基法上も問題ありません。
-
Q賞与や退職金の扱いはどうなりますか?A残業代の扱いと考え方は同様となります。
-
Q産休/育休などはどのような影響がありますか?A産休/育休の取得自体には影響ありませんが、産休時の出産手当金、 育休時の育児休業給付金は、産休もしくは育休前の給与又は標準報酬月額が基礎となりますので、支給額に影響があります。
-
Q住宅ローンについて、減給された金額で審査されるのでしょうか?Aそのとおりです。ただし、家を購入することで、社宅制度を利用しない場合は、減額前の給与に戻るため、社宅制度が適用される前の給与明細や源泉徴収にて確認いただけないか交渉することは可能です。
-
Q役員社宅についてA一般的には家賃の50%までを会社負担にしても損金算入できるようです。 例えば20万円の家賃であれば、10万円分を会社負担で経費計上(損金算入)、残り10万を役員報酬から減額(取締役の報酬 なので株主総会決議等が必要、会社法第361条第1項)とすることが可能です。なお、税務調査に備えて役員社宅を行う上では事前に役員社宅に関する内規を定める必要があります。 ただし、お客様の顧問税理士に確認をしていただき、ご判断いただくようにお願いいたします。











