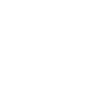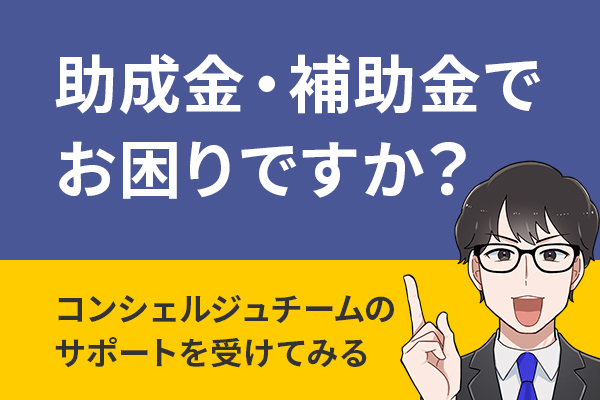助成金の不正受給が発覚したら?罰則や返還リスクを解説
2025年8月5日

目次[開く]
助成金の不正受給とは?
助成金の不正受給とは、本来の支給要件を満たしていないにもかかわらず、虚偽の申請や偽りの書類を作成し、助成金を受け取ろうとする行為を指します。
例えば、実際には雇用していない従業員を雇用していると偽ったり、事業活動の内容を誤って報告するケースが該当します。
不正受給が発覚すると、支給の有無に関わらず、法的な処罰を受ける可能性があります。
詐欺罪や公文書偽造罪が適用され、懲役刑や罰金が科されることもあり、また、不正に受給した金額の返還が求められるだけでなく、追加のペナルティや企業名の公表などのリスクも伴います。
不正の意図がなくとも、確認不足などによる誤った申請も不正受給と見なされる可能性があります。助成金の申請は慎重に行い、適正な手続きを徹底することが重要です。
不正受給が発覚した場合の罰則
助成金の不正受給が発覚すると、以下のようなさまざまな影響がでます。
- 詐欺罪が適用される犯罪行為
- 返還請求と経済的なペナルティ
- 信用の失墜と事業への影響
これらのケースは、それぞれ起こることもあれば、全て該当することもあります。
さらに、助成金や補助金を受給せずとも、不正を目的に申請した時点で不正受給に該当します。
それぞれ、以下で詳しく紹介していきます。
詐欺罪が適用される犯罪行為
助成金の不正受給が発覚すると、不正に関与した個人や法人などの事業所に対し、詐欺罪(最大10年の懲役)や補助金適正化法違反(5年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいは双方の併科)が適用される可能性があります。
また、不正に関与した人物も共犯として処罰される可能性があります。
返還請求と経済的なペナルティ
不正受給が発覚した場合、受給額の返還が求められます。
請求される金額は以下の3つの合計額です。
- 不正発生日を含む期間以降の全額
- 不正受給額の2割相当額(違約金)
- 延滞金
また、不正受給日から5年間は、不正受給を行った以外の助成金を含む雇用関係助成金が受給できなくなります。
信用の失墜と事業への影響
自主申告ではない不正受給が発覚した場合、取り消した支給額が100万円以上であれば、例外なく事業主名などが公表されます。
これにより、取引先や顧客からの信頼を失い、事業継続に問題が生じる可能性があります。
不正受給の具体的な事例
ここでは、実際に発生した助成金の不正受給に関する具体的な事例を紹介します。
不正受給はさまざまな要因で発生しています。具体的な事例を確認し、適正な申請の参考にしてください。
「雇用調整助成金」の事例
雇用調整助成金に関する不正の代表例として、実際には休業していない従業員を休業扱いにするケースがあります。
特に、新型コロナウイルスの影響で手続きが簡素化された特例措置期間の不正が目立ち、特例措置は2023年3月末に終了しましたが、その後も不正受給の発覚が相次いでいます。
株式会社東京商工リサーチによると、雇用調整助成金の不正受給件数が、2020年4月からの累計で1,545件に達したと発表されました。不正受給総額は494億5,939万円にのぼります。
助成金を適正に受給するためには、要件を十分に理解し、正確な申請を行うことが重要です。
参考:株式会社東京商工リサーチ|「雇用調整助成金」の不正受給公表1,545件 愛知県が200件超、サービス業他が半数占める
「持続化給付金」の事例
持続化給付金の申請受付は終了しておりますが、不正受給の事例としてご紹介します。
- 事業をやっていないのに架空の会社と偽って申請する
- 売り上げが減少したと虚偽の報告をして申請する
- 売り上げの減少理由がコロナ禍ではないのに申請する
中小企業庁によると、持続化給付金を不正に受給した者として2,369者を認定し、公表されています。2025年1月31日時点の不正受給は、総額24億1,412万7,924円です。
2,369者のうち、1,773者は、不正受給金額(総額17億9,935万680円)に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を国に対して納付済みです。
参考:経済産業省「持続化給付金の不正受給者の認定及び公表について」
ここまでは故意に不正をした事例を紹介してきました。
また、悪意を持った不正以外にも、不正受給に該当することもあります。
「知らなかった」では済まされない不正行為
雇用調整助成金では、気が付かずに不正受給の要件にあてはまってしまうケースがあります。
例として、次のような事例が考えられます。
- 休業中の従業員が自宅にパソコンを持ち帰り、自宅で仕事を進めていた。タイムカードを押していないので事業主は分からず、雇用調整助成金を申請。
後日、調査によって従業員のパソコンから休業期間中に仕事をしていた記録が残っており、不正受給に該当してしまった。
事業主は従業員の雇用を守るために雇用調整助成金を申請し、一方で従業員は、休業中の空き時間を利用して、できる範囲で業務を進めていた。
このように、お互いを思いやりながら行動していたとしても、申請内容と実態に違いがあれば、不正受給と判断されます。
不正受給を避けるための注意点
不正受給を避けるためには、適正な申請が重要です。
申請時には、必要な書類を全て揃え、正確な情報を提供することが求められます。申請内容に不備や虚偽があると、不正受給と見なされる可能性が高まります。
不正受給を防ぐには、次のような方法があります。
- 締め切りに追われないよう、余裕を持って準備する
- 複数人でチェックし、記載ミスを防ぐ
- 意図せぬ不正を防ぐため、正確な申請を徹底する
詳しくは以下で説明しますが、もしも不正や不適正を見つけたら、速やかに自主申告をすることをおすすめします。
不正受給に該当した場合でも、下記の条件を全て満たすと、事業主名の公表を防ぐ可能性があります。
- 労働局による調査の前に自主申告を行う
- 返金命令後1か月以内に全額納付する
- 不正の内容などが確認され、重大または悪質ではないと認められる
不正を見つけた場合は、速やかに申請した都道府県労働局にご連絡ください。
それでは、不正受給を防ぐ方法について紹介していきます。
1.締め切りに追われないよう、余裕を持って準備する
申請期限が迫ると、根拠のない数値を記入してしまうリスクが高まります。
また、急いで資料を作成すると、記載漏れや誤りが発生しやすくなり、準備するべき書類の不備などがでる可能性があります。
適正な申請を行うためには、最低でも提出期限の2か月前から準備を始め、余裕を持って進めましょう。
2.複数人でチェックし、記載ミスを防ぐ
助成金の申請書は正確性が求められ、書類のミスが不備に留まらず、不正の原因となることもあります。
そこで、代表者と総務担当者など複数人で作成・確認することで、作業負担を分散でき、誤記載のリスクを減らせます。
二重チェックを徹底し、正確な申請を心がけましょう。
3.意図せぬ不正を防ぐため、正確な申請を徹底する
助成金の申請において、不正受給は絶対に避けなければなりません。
意図的でなくとも、誤った数値を記載した場合、不正とみなされることがあります。
「分からないから、これでいいや」「時間がないから、このまま提出しよう」という気持ちで書類を完成させず、申請内容を正確に確認し、曖昧な情報を記入しないようにしましょう。
専門家に相談し、申請をスムーズに進める
申請手続きに不安がある場合は、専門家に相談すると安心です。
制度の変更や最新情報にも精通しているため、適切なアドバイスを受けることで、スムーズに申請を進められます。
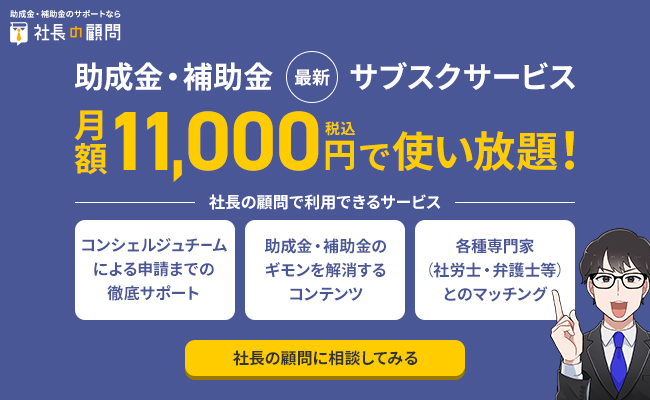
「社長の顧問」では、月額11,000円(税込)で、コンシェルジュチームが活用可能な助成金・補助金を調査し、ご提案します。
助成金・補助金によって準備する書類の量なども違うので、書類の準備にかかる期間などについてもご相談いただけます。
申請代行を依頼したい場合は、単発で依頼できる専門家をご紹介することも可能です。
(※専門家への相談や申請代行には、別途費用がかかります)
まとめ:助成金不正受給を防ぐためには
助成金を正しく活用すれば、事業の健全な成長を支える有効な手段となります。
しかし、「これくらいなら大丈夫」「バレないだろう」といった安易な考えで申請すると、不正受給につながる可能性があります。
発覚すれば、返還請求や罰則を受けるだけでなく、企業の信用も大きく損なわれますので、適正な手続きを徹底しましょう。
「助成金・補助金の知識」
の記事

助成金は何でこんなにめんどくさいんだ!その正体と解決方法をご紹介
「助成金を申請するために色々調べたけれど、結局分からなくなって諦めた」 「助成金申請はめんどくさいと聞いて、二の足を踏んでいる」 「いろいろとやってみたけど、助成金申請が進まず途方に暮れている」 そんな人も多いのではないでしょうか。 数ある助成金の中から1つを選ぶのは大変で、申請作業はもっと大変です。 そこでこの記事では、「めんどくさい」と感じてしまう要因を見極めて、一歩前に踏み出すための解決方法をご紹介します。 助成金はめんどくさいのではないか?と一歩踏み出せていない人や、踏み出した道が険しくなって抜け出せない人は、この記事をきっかけに進んでいただければ幸いです。
2025年12月9日

【店舗運営に活かせる助成金】膨らむ理想を支援制度で現実に!
店舗運営を始める際に、「改装費が足りない」 「設備投資の資金を確保したい」 「かっこいいウェブサイトを安価で作成したい」 など、資金面の課題に直面することは少なくありません。 こうした費用を抑えつつ、理想の店舗づくりを実現するために、助成金や補助金の活用を検討してみてはいかがでしょうか? ただし、助成金や補助金にはさまざまな種類があり、自社に適したものを見極めるだけでも大変です。また、申請手続きが複雑で、後払いが基本といったハードルもあります。 準備不足のまま進めると、受給できないケースも多いため、事前の情報収集が欠かせません。 本記事では、店舗運営に役立つ助成金・補助金の種類、申請時の注意点を詳しく解説します。資金の負担を抑えながら、理想の店舗を実現するために、ぜひ参考にしてください。
2025年8月5日

2025年育児・介護休業法改正:6つのキーワードで分かりやすく解説
2025年4月から段階的に施行される育児・介護休業法の改正は、柔軟な働き方を促進し、離職防止を図るため、事業主に新たな対応が求められます。 本記事では、改正内容を11のポイントに整理し、企業が準備すべき具体策を6つのキーワードでわかりやすく解説します。 施行日までにしっかりと対応を進め、働きやすい環境づくりを目指しましょう。 また、法改正への対応にあわせて活用できる助成金についても紹介していますので、ぜひご覧ください。
2025年8月5日

助成金申請の落とし穴?提出先を間違えないための申請初心者向けガイド
助成金を申請する際、提出先や手続きの方法を正確に把握していますか? 助成金の申請窓口は、種類や地域によって異なるため、事前の確認が不可欠です。 助成金は1種類でも、申請書類は複数あり、書類によって提出する先が変わることもあります。 本記事では、助成金の提出先や窓口ごとの特徴、提出方法を具体的に解説するとともに、申請手続きをスムーズに進めるコツもお伝えします。 初心者でも安心して活用できる情報を掲載していますので、ぜひお読みください。
2025年12月9日